は「政府の方針はわかりづらく、しばらく混乱は続くだろう。そもそも日本人は責任回避の意識が強く、物事を自分で決めようとしない。いい加減、そうした事なかれ志向から脱却すべきだ」という──。
■とにかく「決める」ことが苦手な日本人
日本人は、とことん「決定する」ことが苦手な人々だ。理由は、何かしらの決定をしてしまうと、その後の動向次第では自分に非難が寄せられてしまうからである。
とりわけ、斬新な案(見方によっては過激な案)や、実現の困難さが指摘されそうな案は、議論の俎上(そじょう)に載せられる前に引っ込めてしまうことが大半だ。良好な結果が出なけれ
ば「なんであんなに極端な案を採用したんだ!」「『難しいのではないか?』とオレは事前にさんざん言っただろ!」などと叩かれ、時には社会的に抹殺されてしまう。それを恐れて、何事も無難な方向へ収束させていく。
日本人は「和を以て貴し」を美徳とするあまり、何をするにも周囲の顔色をうかがう悪癖が抜けず、集団のなかで孤立しないために安パイばかり選んでしまう民族である。そうした風土が
あるので、冒険心に溢れたプランや急進的な案を採用して失敗した場合は猛烈に叩く一方、無難なアイデアを採用して失敗した際には「結果的に傷は浅く済んだ」「当時は、あれが最良の判断だった」などとなれ合い的に落着させてしまう傾向が強い。
マスクも然りだ。「マスク着用は個々人の判断」となった2023年3月13日、ツイッター上では「みんなマスク着けてる」「マスク率99%」といった報告が数多く見られた。「花粉症だから
ね」という一文がエクスキューズのように添えられたツイートも見られたが、日本人って99%が花粉症だったんか? 結局「他人の目」対策であろう。
私は今年2月10日に発表された「3月13日以降、マスク自由化」の報を受けて、「マスクを着けて家を出て、周囲の人々の様子を見てからマスクを外すか、外さないかを判断するだろう」
「最寄り駅の改札を通る際には外していた人であっても、再度着用するだろう」と予想した。実際、そのとおりになったようだ。「他人の目」対策だけはバッチリである。
■意志決定しても中途半端な結果で終わる理由
そもそも「意思決定」とは、誰かにとってはよい結果をもたらすが、別の立場の人にはあまり望ましくない結果をもたらすこともある営みである。ゆえに議論が必要になるのだが、この議
論が「無難」「どちらの立場にも配慮」といった意識に支配されてしまうと、効果が最大化されなかったり、中途半端な結果で終わってしまったりする可能性が高くなる。
たとえば、ある課題を解決しなければならない場面で、Aの立場を取る人、Bの立場を取る人が、それぞれ同数いたとしよう。そこで「革新的な“プラン1”の方向に果敢に振り切ることがで
きれば、全体的なメリットの値は90~100になる。だからこちらを採用しよう」という意見が出された。しかしこの意見に対して、別の人間が「何事も『振り切る』のはよくない。Aの人
にはいいが、Bの人の一部は不利益を被る『かもしれない』から配慮が必要だ。禍根を残してはいけない」などと反論する。そうして最終的に「両者に配慮する」ことのみを念頭に置き、
全体的なメリット値は60~70に下落するものの、とにかく無難な“プラン2”が最終的に採用される……といったことが、日本社会ではまま起こる。
“プラン1”を採用していれば、Bの人が受けるデメリットは最大でも10で済んだのに、“プラン2”を採用した結果、Aの人とBの人がそれぞれ15~20のデメリットを甘受しなければならなく
なるとしたら、どちらのプランを採用するのが全体最適として合理的な判断だろうか。結局、「配慮」「無難」を優先するばかりに、「合理性」を犠牲にするのが日本人の意識決定なの
だ。本稿では、ここまで述べたような日本人の意思決定パターンとプロセスについて考えてみる。
■日本人に根付く「後で怒られたくない」という行動原理
日本人が何かしらの決断を迫られた場合、基本的には「後で怒られたくない」という心性が行動原理になることが非常に多い。
昔から不思議だったのだが、サッカーの試合、それこそFIFAワールドカップのグループリーグの試合であろうとも、日本人のフォワードはシュートを打たないことが多かった。さすがにレ
ベルの上がった2022年カタール大会の日本代表では、そのような場面はあまり見られなかったが、昔はその傾向が強かった。
もっとも印象深いのは、2006年ドイツ大会のクロアチア戦だろう。右サイドから切り込んだディフェンダー加地亮が、ペナルティーエリア内で絶妙なパスをフォワードの柳沢敦に出した。
相手キーパーは加地の方向に向かっており、柳沢はボールを靴の内側に軽く当てさえすれば、無人のゴールに入れるだけの「ごっつあんゴール」が獲得できるはずだった。しかし、柳沢は
慌てたように靴の外側でボールを受け、あろうことかゴールの枠外にいるキーパーの股の間を通す形でパスを出し、ボールは場外に流れていった。試合後、柳沢は「急にボールが来たので……」とインタビューに答え、「QBK」というネットスラングが誕生した。
当時、柳沢に対しては「プレースタイル的に『得点をお膳立てするフォワード』といった役割があるから、そんなにバシバシと点を取ろうとしなくていい」といった擁護の声もあった。だ
が、あの決定的な場面ではさすがに点は取るべきだろう。柳沢だけでなく、かつての日本代表
のパス回しを見ていると、バックパスは多いし、とにかく自分のところに来たボールのことを
「こんな厄介者はあっち行け! オレの責任外のところに行ってくれ!」と思っているのでは、とさえ感じることが多かった。
柳沢も「オレはゴールを決めることより、他の選手が決めやすい状況をつくるのが仕事だ」と考えていたのだろうか。だから「急にボールが来た」と釈明し、決められなかったことを正当
化したかったのかもしれない。「ここで決めればオレはヒーローだ!」といったメンタリティではなく、「もし外したら、後で怒られる」といった思考が先立ち、ゴール前でとっさに消極的な動きをとってしまったのでは、とも思った。
■何よりも「批判」を恐れる。だから絶好機を平気で逃す
柳沢に限らず、当時のサッカー日本代表にはここぞという場面で消極的な動きが目につく選手が多かった。
「少しでもミスをしたら怒られる」「後で苛烈なバッシングにさらされてしまう」などと、チーム全体がある種の恐怖感に支配されていた可能性もある。だとすれば、ペナルティーエリア
内でボールを受けたフォワードやミッドフィールダーが、そこで自らシュートを打つより、「もっとシュートが入りやすそうな選手は他にいないだろうか」と探してしまうのもやむを得
ないのかもしれない。もしかしたら柳沢も、ここまで素晴らしい機会が自分に来ると思っておらず、高速で走ってくる加地にナイスなお膳立てパスを出すことこそ最重要だと思ったのでは。まあ、非常に情けない姿勢だし、個人的にはまったく共感できないが。
「自分がリスクを背負ってゴールを外すより、確実性が高そうな選手に渡して得点の可能性を高めたい」とギリギリまで考えるのもひとつの選択だが、その0.何秒かの判断の遅れで、相
手にボールを取られてしまうこともある。だったらさっさと強烈なシュートを打って、相手のキーパーやディフェンダーにボールを当て、そのこぼれ球を誰かが押し込む……といった判断のほうがいいのではなかろうか。
「サッカーの素人が何を言っているのだ!」と言われるかもしれないが、こちらはサッカーの素人ではあるが、サッカー観戦歴は40年を超えたれっきとしたベテランである。ゴール前でシ
ュートを躊躇する様は、見ていてイライラするサッカーだ。トップレベルの選手でさえそうなのだから、その下のレベルだとさらにその傾向は強いだろう。小中学校レベルでは、よほど
「無双」できる選手はさておき、自分がゴールを決めてヒーローになる喜びよりも、ゴールを外して戦犯扱いされることを恐れてしまうのではないか。
■過度な安全志向が「中庸」な案を生む
最近聞いた話によれば、とある役所では「何もしない人が出世しがち」なのだという。「何もしない人」「何も決めない人」は失敗しないから、というのがその理由らしい。決定者になら
ないこと、問題を先送りすることこそ、減点方式の評価がまかり通る日本ではもっとも賢い処世術なのである。
日本ではビジネスの世界でも学校でも、とにかく「何か問題があった際には怒られないように立ち回ろう」「問題が発生したとしても『最善を尽くした』と言えるようにしよう」といった考え方に陥りがちである。だから意思決定が遅い。
2022年1月19日、イギリスのボリス・ジョンソン首相(当時)は、イングランドで導入されていたコロナ対策の「プランB」を同月27日に終了すると宣言。これにより、マスク着用義務は終了となった。発表からわずか8日後の決行である。
一方、日本は方針を出した2023年1月27日から約100日後に新型コロナウイルスを5類へ変更すると発表した。日本の意思決定の遅さは、国際競争に臨むにあたり、致命的に足を引っ張る。
なぜ意思決定が遅いかといえば「誰かのメンツを潰すかもしれない」「この決定をしたら不安に思う人がいるかもしれない」「私がここで意思決定をしてしまった場合、上から怒られるか
もしれない。それはなんとしても避けたい」という3つの考えが理由として挙げられる。また「より安全な策を取る」という意識も強いため、波風が立たない形で採用される可能性が高い「中庸」な案を必ず準備しておくことが多い。
■あいまいなマスク着用の方針が示された
この「中庸」というヤツが実に厄介で、そうした方向性の案を採用した場合、その後の意思決定が大幅に遅れてしまうのだ。それがよく表れたのがマスクの扱いである。前述したように、
厚労省は2023年2月10日に「マスク着用の考え方の見直し等について」という方針を発表。それまで屋内で推奨されたマスク着用の取り扱いを行政がルールとして求めるのではなく、同年
3月13日以降は「個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本」とする形になった。
文書ではここから説明が延々と続くのだが、読み進めていくと「政府は各個人のマスクの着用の判断に資するよう、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面などを示し、一定
の場合にはマスクの着用を推奨する」という一文がシレッと登場する。個人の判断である、と述べつつも、これを読んだ施設などが「要するに、これからもマスク着けてもらわなくちゃい
けない……ということかな」と忖度(そんたく)する余地を十分に残している。そんな、あいまいでつかみどころのない指針が示されたわけだ。
適用される日付が3月13日というのも謎である。あのさ、12日まで着けていたマスクを13日から外せることにした根拠はなんだ? どうせ「発表から1カ月後あたりで、ちょうど週初めの
月曜日だから、まあ、いいタイミングじゃないすか」程度の理由だろう。科学的な根拠は一切ない。文書はそこから先もダラダラと注意事項が並び、満員電車では着けろだの、特急列車で
はそれほど必要ないだのと言い連ねる。着脱について差別するな、などと白々しく付け加えることも忘れない。そして結果は、マスクマンだらけの通勤・通学風景や、電車内の様子を見れば明らかである。日本人は、まだまだマスク生活を継続したいらしい。
■政府やメディアがアナウンスすべき要点は3つにまとめられる
コロナ対策においてマスクが無意味なことは、もはや明らかである。持って回った内容の文書で事業者や国民をむやみに混乱させるのではなく、政府やメディアがアナウンスすべき事柄は、端的に以下の3点だと考える。
【2】日本ではもはや、効果うんぬんではなく、「他人の目」対策でマスクを着用しなければならない空気になっている。そうした風潮は、もう終わりにしよう。
【3】「マスクを着けていない人」のことを恐れる人々に、これ以上、社会全体が合わせる必要はない。
これらのメッセージを発したうえで、「着けたい人は着けてください、着けたくない人は着けなくて構いません。皆さんの自由です」で終わりにすべきだったのだ。
■一部の人々が「マスクを外されるわけにはいかない」と考えている
ニューヨークタイムズのコラムニストであるブレット・スティーブンス氏は、2023年2月21日の電子版で「TheMaskMandatesDidNothing.WillAnyLessonsBeLearned?」というコラムを発表した。
タイトルを和訳すると「マスクの義務化は意味がなかった。ここから何か教訓は得られるのか?」となる。同コラムは、イギリスの権威ある医療・予防情報提供組織「コクラン」に、
「新型コロナウイルスの対策として、マスクには効果がない」と示す論文が掲載されたことを受けて著された。
これまで発表されてきた「マスクには効果がある」と言い張る論文などは、そう主張するために都合のよいデータを集めて書かれたものにすぎない。今回、コクランに掲載された論文は、
世界61万827人が参加した78のRCT(ランダム化比較試験:もっともバイアスがかからないとされる試験。そのうち6つは新型コロナ関連)をベースにしたものだ。
コラムの一節を私なりに訳してみたので紹介しよう。
どんな研究、もしくは研究の研究も、これまで完璧だったことはない。科学とは、絶対に完全なる結論がでるものではない。だったら何を言いたいか。これらの分析によると、適切なマス
ク、そして適切な着用方法には、個人レベルでは何も利点がなかったのだ。個々人はマスク着用で得られる自分なりに合理的な理由を持っていることだろう。そして彼らには、常にマスクを着用する忍耐心があった。それは彼ら自身の選択である。
しかし、集団レベルでのマスク着用の利点ということになると、評決はこうなる。「マスク義務化はクソだ」。効果に疑問を持っていた人々は、効果があると考える人々から苛烈なまでの
嘲笑とともに変人扱いをされてきた。さらに義務化が正しいと考える人々からは「デマ野郎」扱いさえされた。多数派である、マスク義務化を支持した専門家らは間違えていたのである。
もう少しまともな世界であれば、こうした専門家の過ちこそ指摘すべきだった。それは、身体的、精神的、教育的、そして政治的コストも考慮のうえで。
まったくもって、そのとおりである。マスクに意味はなかった。しかし、パンデミックが続いていることを視覚的に示すため、さらにはワクチン接種へとつなげていくため、マスクは一部の人々にとって、「民衆から外させるわけにはいかない」アイテムになったのだ。
■「マスク警察」活動に勤しんできたテレビ
最近、日本のテレビは街頭インタビューなどで「顔を見せるのが恥ずかしい」「マスクが当たり前になってしまったから、外すことに抵抗がある」「個人の判断になったとしても外さない
と思う」といったことを語る人々をやたらと登場させ、マスク社会を終わらせないよう頑張っている。
メディア業界に身を置く私の想像ではあるが、メディア人というものは過去の論調を覆されたり、誤謬について指摘されたりすることを極端に嫌う。この3年間、テレビはマスクの効果に
お墨付きを与え、マスクこそが「コロナとの闘いに勝利するカギだ」と触れまわってきた。さらに、飲み屋の客や自転車に乗る人を盗撮しては「アッー! マスクを着けていない人がいます!」などと積極的に「マスク警察」活動に勤しんできた。
緊急事態宣言に伴って飲食店が酒類の提供を中止した際、テレビはやたらと「路上飲み」を問題視していた。外で飲んでいる人々のところへリポーターが突撃し、「いま、マスクを外して
いましたよね?」などと詰問する映像をおぼえている人も多いだろう。テレビこそが最大のマスク警察だったため、このところ強まっている脱マスクの風潮を受けて「マスクを外す流れを
阻止せねば」と考える向きもテレビ関係者に存在するのではなかろうか。腐ったメディア人だ。過ちはさっさと認めろ。貴殿らにメディアの仕事をする資格はない、卑怯者め。コロナ対応の趨勢はすでに決しているのだ。
■小役人のメンツに国民全員が付き合わされている
私はいま、日本の「マスク圧」のバカさ加減にあきれ果て、タイにいる。こちらでは、先ほど紹介したニューヨークタイムズのコラムにある指摘のとおり、「着用したい人はして、着用し
たくない人はしない」「他人はその判断に干渉するな」という空気感である。実に快適だ。そして、この空気感は日本においてもさっさと広まるべきである。
にもかかわらず、無難であること、波風が立たないことを旨とする過剰なまでの安全志向、そして「責任を取りたくない、責められたくない」という思考にとらわれた小者の跳梁跋扈(ち
ょうりょうばっこ)により、日本のマスク生活は「3月13日以降は個人の判断」という指針が示されても終わらなかった。
こうした状況を生んでいるのは、いまだにマスクの効果をうたい、安全策を取ろうと躍起になっている厚労省である。この期に及んでもまだ「いや、オレら、マスク外すのに全面的に賛成
したわけじゃないから……」と逃げを打っている。国民の健康を司る省庁が「マスクこそ、至高のコロナ対策!」と激しく旗振りをしてきのだから、もはや撤回はできない。結局、小役人のメンツに国民全員が付き合わされているのだ。
というか、実態としては「素顔恐怖症」の人々に配慮をしまくっているだけである。クレームが怖いからだ。マスクを外した後に陽性者が増えた場合のことを想定し、「批判されないよう
にしよう」と保身に走っているだけである。着けたい人は着け続け、着けたくない人はさっさと外す。互いに干渉しない。それだけで終わる話に「ガイドラインガー!」などとウダウダ言い連ね、両方の人間に配慮したふうを装っているのだ。
■マスク着用はこれまでも任意。これからも任意
「マスク着用の考え方の見直し等について」の発表後、東京都から飲食店や各種施設に以下のようなメールが届けられたという。
「マスク着用」の取り扱い等の見直しについて(令和5年3月13日から5月7日まで)
見直しのポイントは次のとおりです
・3月13日(月)から、マスクの着脱は個人の判断が尊重されることとなります。
・ただし、各店舗が感染対策上又は事業上の理由等により、お客様や従業員にマスクの着用を求めることは可能です。
・3月13日以降も引き続き、効果的な換気、手指消毒、距離の確保又はパーテーションの設置等、マスク以外の感染防止対策に取り組んで頂くようお願いします。
要約すると「マスク着用については個人の判断を尊重してね」「ただ、客にも従業員にも、施設側の判断で着けるよう求めることはできるからね」「今後も感染対策、頑張って」というこ
と。つまり、これまでと何も変わらなかったのだ。3月13日までもマスク着用は「任意」だったのだが、改めて「任意」であると明言されたにすぎない。「これまで任意だったけど、これからもやっぱり任意だよー」ということ。もはや茶番である。
もっとも、変わらないのは国民も同じだ。たまたま日本のテレビニュースを見ていた折、マスク着用が個人の判断になることを踏まえて、子どもを持つ親たちに意見を聞くインタビューコ
ーナーが流れた。そこに登場した母親たちは「親としては、もう少し様子を見たい」「完全に安全になったと思ってからマスクを外させたい」といったことを語っていた。国民が万事この調子だから、社会の空気もなかなか変わらないのである。
■中庸な落としどころにこだわり、東京五輪は無観客開催に
コロナに関連する最大級の「両方の顔を見る」判断は、東京五輪の無観客開催だろう。後に尾身茂・政府分科会会長は、『中央公論』(2021年11月号)のインタビューで「観客を入れて
も、私は、会場内で感染爆発が起きるとは思っていませんでした」と答えている。五輪実施を「普通ではない」とまで断じた男が一体どの口で言うか、である。
加えて、それでも無観客を要求した理由については「観客を入れたら、テレワークなどによって人と人が接触する機会を少なくしてほしいと国民に求めていることと矛盾したメッセージを
送ることになります」と説明した。完全に科学者の発言ではない。まるで政治家のそれである。こんな男に日本はコロナ対応の舵取りを任せてきたのだ。
こうした尾身氏をはじめとした専門家やメディア、そして反政権派は「五輪を開催したら人が死ぬ」「東京五輪において、極悪ハイブリッド株が爆誕する」「世界中から人々がやって来て
コロナを蔓延させ、東京はヒドいことになる」といった論を繰り出し、五輪を中止に追い込もうとした。そうしたなかで、両側の顔色をうかがいながらひねり出された中庸な結論が「無観客開催」だったのだ。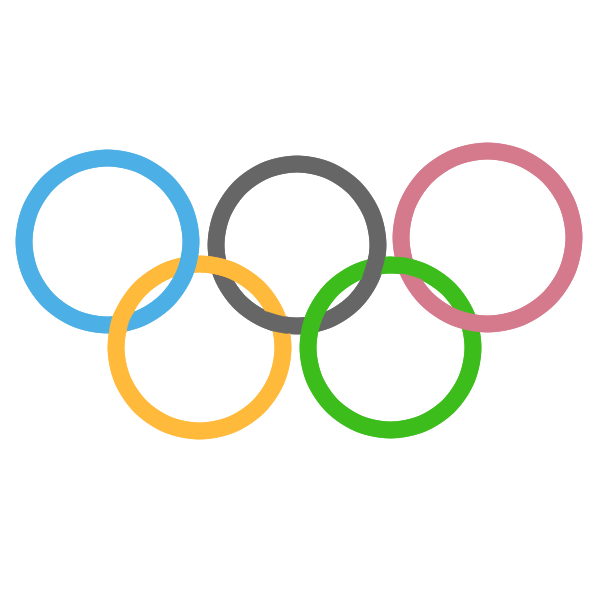
■人々の恐怖心を自らの人気取りに利用した政治家たち
実際に大会が開かれるまで、東京五輪には「恐怖」「不気味」「不審」といった強い負の印象が常に付きまとっていたわけだが、それらネガティブイメージを自身の支持率上昇、「誠実に
仕事に取り組んでいる」感の醸成、「頼れるリーダー像」の演出などに小賢しく利用したのが、政治家である。
一例を挙げよう。2021年5月21日、読売オンラインに「五輪『もしやったら、日本は滅亡するのでは』…市長が危機感」という記事が掲載された。
この頃は「反五輪」の風がもっとも強く吹いており、両側の顔を見ながらバランスを取るような雰囲気も弱く、片側(反五輪)の支持だけを集めることのほうが重視された。何しろ「命」
を持ち出せば、なんでもかんでも中止にできた時期なのだから。
記事を一部引用しよう。
「命を守ることが一番だと思うので、オリンピックには反対」――。埼玉県坂戸市の石川清市長は20日の定例記者会見で、記者からコロナ禍での東京五輪開催の賛否を問われ、反対の考えを明らかにした。
石川市長は、新型コロナウイルスが感染拡大する現状について「感染症との戦いの中でも異常なものだと思う」との認識を述べた。
五輪については「感染者は昨年よりずっと多い。変異型も出ている。国はやる方向だと思うが、もしやったら日本は滅亡するんではないかな、と思うくらいの危機感を抱いている」と語った上で「政治家は嫌われても、決断するときはするべきだ」として、中止の考えを訴えた。
■いくら行政がアナウンスしても、日本人はマスクを外さない
終わってみれば、東京五輪は「殺人五輪」になどならなかったし、多くの国民は日本のメダルラッシュに沸いたわけだが、開催前はとにかく「安全策を取るべき」に類する発言をすれば支
持されるような、異常な状況だった。結果的に誤った判断、ピントのずれた指摘だったことが後日明らかになったとしても、提案をしたり、決断を下したりした人は怒られない空気感すら存在した。「あのときの判断としては妥当」となっていたのである。
そうしてマスク着用生活が2年を超え、海外のスポーツイベントなどではマスクをしている観客のほうがレア……という状況が日本にも伝わるようになってきた2022年5月20日、厚労省は
世界からだいぶ遅れて「屋外では原則、マスクを着ける必要なし」という基準を公表した。もっとも、厚労省がいくらアナウンスしても、マスクへの過度な信頼(信仰⁉)が捨てられない
日本人は、その後も屋外でマスクを外すことはなかったのだが。今年3月13日以降も、そうした空気は変わらなかった。
「私は花粉症がヒドいからしばらく外せない」「メイクに力を入れないで済むから便利」「ヒゲをそらないでいいからラク」「もう顔の一部になってしまったから、すぐに外そうとは思え
ない」など、外さない理由を個々人が言い訳がましく述べている状況だ。どうせ花粉症の時期が終わっても、「黄砂やPM2.5が来るから外せない」などと言うのだろう。
■決断できない日本人は、まわりくどいガイドラインに翻弄される
厚労省が示したマスク着用のガイドラインは本当に説明がまわりくどく、両方の顔色をうかがう及び腰の姿勢に満ち満ちている。こんな基準を提示されても、決断力に乏しい日本人はマス
クを外せない。余計な条件など並べ立てず、「原則、屋外ではマスク不要」「外したい人は外し、外したくない人は着けたままで構わない」「外さない人は、外した人を差別しない」の3点を述べるだけでよいのに。
せっかくなので、厚労省が示した責任回避の名文を紹介しておこう。
・屋外では、人との距離(2m以上を目安)が確保できる場合や、距離が確保できなくても、会話をほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要はありません
・公園での散歩やランニング、サイクリングなど→マスク必要なし
・徒歩や自転車での通勤など、屋外で人とすれ違う場面→会話をする場合は着用を推奨
・屋内では、人との距離(2m以上を目安)が確保できて、かつ会話をほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要はありません
「外していい場面」をいちいち例示するとは、何とも過保護である。屋内で着用が「推奨」されるのは「会話時」となっているが、2m以上離れた会話の場合は、推奨はされつつも「十分
な換気など感染防止対策を講じている場合は外すことも可」だという。また、「会話をほとんど行わない場面」としては、図書館での読書や芸術鑑賞が挙げられている。これらの記述を見
ても、指示待ち人間が多い日本人は「だったら常時着けておこう」となるに決まっている。なお、「通勤ラッシュ時や人混みの中ではマスクを着用しましょう」とのこと。さらに高齢者と会うときや病院へ行くときはマスクを「着用しましょう」としている。
このガイドラインを読んだ博物館の職員などは「図書館や美術館は会話をほとんど行わない場面扱いされているが、博物館は挙げられていない。よって博物館は対象外なのだろう。マスクは着用してもらおう」と判断してもおかしくない。
■日本人の意志決定スタイルは仕事にも頻用される
こうした日本人的意思決定スタイルは、一般的な仕事の現場でも多用される。私がもともと働いていた広告業界はその傾向がとりわけ強い。たとえば、プレゼンに臨むにあたり、アイデアを3案用意する、といった「お約束」もそのひとつだろう。
広告会社のクリエイターやプランナーが「今回は、この渾身のアイデアひとつで勝負しましょうよ!」と社内の打ち合わせで営業担当に提案したとしよう。すると、クライアントと日常的
にやり取りし、常に顔色をうかがって先読みする意識が強い営業担当者は、大抵の場合こう返してくる。
「いや、クライアントには選択肢を与えたほうが、絶対に心証がいい。仮にその一本で勝負した場合、クライアントが気に入らなかったら即、負けが決まってしまう。松竹梅の3つの選択肢を提示して、選んでもらうべきだ」
このような場合では、「松」がもっともぶっ飛んだアイデアであり、「竹」は中庸、「梅」は面白くもなんともない平凡なもの……というのが相場だ。そして、提案を受けたクライアント
が社内会議で「揉んで」みた結果、選ばれるのは大抵の場合「竹」なのである。さらに、その「竹」案が通ったとしても、クライアントは追加でこう依頼してくることがたいへん多い。
「この『竹』案をベースに、若干『松』の奇抜さや斬新さ、『梅』の慎重さをまぶすような方向で再提案してもらえないか」
広告施策には多額のカネが動くので、失敗する可能性は極限までそぎ落としたいし、何かを選択するにしても慎重になるのは理解できる。だから大企業のCMでは有名タレントを起用して
最低限の安心材料をまず確保する流れになりがちだし、無難でつまらない演出に落ち着くことが多いのだ。私は4年で広告代理店を辞めたが、この手の中庸さ、無難さが求められること、
そしてプランナー側の裁量が少なすぎることに辟易としたことも、退職を決意した理由の一部になっている。
■幼稚な意志決定プロセス、責任回避思考をどうにかせよ
少し余談になるが、その後、私はフリーライター・編集者となり、雑誌とネットニュースの制作に関わるようになる。両方ともそれほど大きなカネが動くわけでもないから、ひとりの編集者の権限で「エイヤッ」と大抵のことはできてしまった。
雑誌『テレビブロス』では6ページのバカ特集をさんざん作ってきたが、編集長は何も口出しをしてこなかった。校了日に「面白いですね」と感想を伝えてくれるだけ。編集長は一貫して
「とにかくバカっぽく作って構わない」と言ってくれたので、たとえば「一人鍋特集」を手がけたときには「まずい鍋TOP10」など、広告案件ではあり得ないような切り口の企画も容赦なく入れたりした。それでいて読者からの評判はよかった。
話を戻そう。冒頭でも述べたように、日本人が意思決定する場面では、とにかく波風を立てないようにし、怒られる人間を生まないことが最優先される。
それこそ広告案件のプレゼンの際にも、こうした責任回避の場面を何度も目にしてきた。プレゼン終了後、こちらが「いかがでしたか?」と相手の現場担当者(普段の業務で接する若手や
中堅)に尋ねると、その人は「検討ですね……」と言いながら隣の上司をチラリと見て、「山田係長はいかがでしたか?」などと尋ねる。すると係長は「検討ですね……」と言い、隣を見
て「吉井課長はいかがでしたか?」と尋ねる。そして課長も「検討だなぁ……」と言い、その隣を見て「近藤部長はいかがですか?」と尋ねる。部長は「検討だなぁ……。マッ、社内で揉
んでお返事しますよ」となる。この場で賛同ないしは否定をしてしまうと、自分の責任問題につながってしまうかもしれない。それを心底恐れているのだ。
実にくだらない。日本が「失われた30年」に陥ってしまった理由がよくわかる。このまま幼稚な意思決定プロセス、そして責任回避の思考を日本人が続けるのであれば、「失われた40年」も視野に入ってくるだろう。
【まとめ】今回の「俺がもっとも言いたいこと」
・日本人は「和」を重んじるばかりに、決断することが苦手な民族である。
・さらに日本人には「後で怒られたくない」「責任を負いたくない」という事なかれ志向がベッタリと染みついている。だから意志決定が遅い。
・コロナ対応でも、そうした日本人の情けない特性が存分に発揮され、あらゆることが後手に回っている。
・幼稚な意志決定プロセス、責任回避思考からいいかげん脱却すべし。
----------
ライター
1973年東京都生まれ。1997年一橋大学商学部卒業後、博報堂入社。博報堂ではCC局(現PR戦略局)に配属され、企業のPR業務に携わる。2001年に退社後、雑誌ライターや『TVブロス』
編集者などを経て、2006年よりさまざまなネットニュース媒体で編集業務に従事。並行してPRプランナーとしても活躍。2020年8月31日に「セミリタイア」を宣言し、ネットニュース編
集およびPRプランニングの第一線から退く。以来、著述を中心にマイペースで活動中。著書に『ウェブはバカと暇人のもの』『ネットは基本、クソメディア』『電通と博報堂は何をしているのか』『恥ずかしい人たち』など多数。
----------

(出典 news.nicovideo.jp)
|
<このニュースへのネットの反応>
他人がマスクしてるだけでここまでなるなら、もう病院いった方がいいんじゃないか
※ニュースではありません チラシの裏にでも書いておくべきな ただの個人的な愚痴です
コロナ以外にも花粉症とかマスクを付ける必要があるから外さないだけなんですけど。外したい人だけが外せばいいのに周りにも外させたがるのが理解できん。
着用しない方がマシなんて科学的な見解もまたないんだよ。自分が着けたくないなら堂々としてろよ。自分がマイノリティだという事実に怯え、批判を恐れて、過剰反応して自分だけが正しい、自分と違う考えは間違ってる、皆自分と同じにすべき、とかいうこういう奴が一番下らない。
なんでマスク外さないことで国民が叩かれなあかんの?
任意なのに何でそこまで言われなきゃならんのだ
花粉症シーズン真っ盛りだアホめ。
猛威振るってた頃に外して感染しておけば良かったのに・・・言葉で理解できないなら体験するのが一番だろ
したいからしてる。なんも変わらない。強要はやめてもらってどうぞ
マスクを外すことを強要するなよ
自分の考えに反するものは認めない差別主義者がなんか言ってる
じいさんの妄想かと思ったら、まだ50じゃないかw
ライターは「任意」という言葉の意味を知らないのか
日本人じゃないから任意って言葉の意味がわからなかった説
しつこいなー、マスごみアホ反日極左は風邪とか花粉症ってものがあるの知らんの? それともそれらが都市伝説とか陰謀論によって生み出されたものだとでも勘違いしてんの?
任意だから着けてます。の何がいけないの?
日本人の「事なかれ志向」は実に情けない>自分と考え方が違うってだけでここまでのマウンティングをしてくるって、絵に書いたような「嫌な奴」だな。
1:マスクで多少なりとも安心感を得られるから【任意で】着用する 2:2018まででもこの時期は花粉があるからマスクしてた まだ何か反論があるかね?
まわりくどいガイドライン<有効な治療薬が市販されるまでで警戒する。ただそれだけでは?
マスクをさせなくして、その浮いた分のマスクをどこにやろうってんだね?
任意なら外すように強要するのは間違ってるんよ
マスクを外したら白い目で見られるから、俺様が安心してマスクを外せるようにお前らもマスク外せよ! ←プレオンの中川というライターの主張はこうですか?
任意なんだから付けていても外していても個人の自由ですよって事ですよね?何で自主的に着けてる人を批判するの?
うるせえ花粉症なんだよ
任意なんだから、つけるのも外すのも自由だろうが。自分の判断でつけることを選んでいる人、外す人どちらもいるが、つけている人に外せと強要するやつは、何をもとにした主張だ?各々が自分の判断ですることを否定するのは、外すことに責任を持てないからで、結局自分で判断ができない人なんじゃないか?
こちとら任意で着けてんだよ!
こんな超長文ゴミ記事を出してまで自己肯定しないとマスク外す勇気が出ないの?
30年前から花粉症で2月中旬からゴールデンウィーク明けまでマスクなんだよねえ。
スペイン風邪を始め「感染症の歴史」を学ぶことが出来る学習環境の国の国民として、各々が選択肢として感染症対策をとる・とらないは自由であっても「マスクを外せ」なんて強要されるものじゃありません。
コロナ前から秋~冬は風邪予防、春~初夏は花粉対策でマスクをしています。仕事もドライにできるし、ねちねちしためんどくさい人間関係とか愛想笑いとかカットできるし個人的には良いと感じることが多い。つまり任意なので好きにすれば良いで解決ですね。
この3年でマスクがどれだけ有用なのか心底理解できたから、この先もずっとマスクしてるわ。月に数百円の小銭で風邪ひかなくて済むんだからな
髭剃り数日さぼってもバレないから楽なんだよ悪いかゴルァ
商店や飲食店にマスク着用を入店の条件にしないように政府が通達を出せ。
今、普通に花粉症の時期やねん。
花粉症の時期に何いってんだ。つーか任意ってことはマスク外すのも外さないのも自由。何で任意=外すの当然になってんだこのやたら長い文書いた奴。
外したら外したらでケチつけてきそう。
アルミホイル足りてないぞ
『着用は任意、個人の判断』なんだから「どうして日本人はいつまでもマスクを外せないのか」「さっさとマスクとおさらばしよう」なんて声高に主張してるやつの方がよっぽどウザいし『強要』だろ。花粉症対策でマスク着用してて何が悪い
大半の人はマスクなんて気にもしてないんだろ。まあ暑くなってくりゃ外すんじゃない?(*´・ω・`)
まあニホンジンガーなんて言ってる奴に外せって言われても聞くやついないわな?これまでもこれからも任意、つまり各自の判断でマスクしてるだけだろう。外させたいバカは批判ではなく外すメリットを語るべきだろうに。まあ*には難しいか
今の時期でマスク外せとか*じゃないのか。花粉症で苦しんでる人が掃いて捨てるほど出る時期だぞ。まあ、空気読めないのは左翼の特徴だからしょうがないんだけどね
50歳児がわがまま大爆発させてるだけだった
マスク着用のお願いを同調圧力と批判してきた奴がマスク外せと同調圧力かけるってこれもうわかんねえな?
花粉症の人が山ほどいるでしょうに。この人そんな想像すら出来ずに皆コロナに対してマスク外せないって思ってるんですかね(嘲笑)花粉症シーズン終わって熱中症の危険性高まる初夏くらいになっても付けてる人が多かったら、多少は賛同する人でてきたんじゃないの。
言っても花粉の時期だしインフルエンザもあるし明確な特効薬の名前も聞かないしでマスクが安パイなんだわ。てか任意とは言え人ごみや病院ではマスク推奨だけどね。
長すぎて読んでないけど、「治療薬もできていない時点で外したくないんだが?」って意志で付けている。任意だし、それ以上でも以下でも無い。大概そんなもんでしょ
えーっと… たかがマスクの話でこんなに長い記事が必要なのかい
今は季節の変わり目だし、花粉の季節だ。普通に付ける人だって多かろう。別にコロナ禍前から人間はマスクつけてたろうが。そもそも他人がマスクつけてるだけで、そこまで飛躍したこと考える方が病気だよ。他人のマスク以前に頭の病院にいってこい
マスク付けると決めた事に対してくやしがる反マスクの嘆きですなw
そもそも新しいマスク基準ってそんなにわかりにくいか?今まで『出来るだけマスクして下さい』だったのが『どっちでも良いよ。常識諸々で考えてね』に変わっただけの話でしょ。
任意と自分で言ってるのに付けてる人が情けないとか攻撃するのが分からない。頭大丈夫?
四六時中アイマスク付けて記事書いてそうな内容ですね これまでもこれからもマスク着用が任意ならマスクなんて付けるなと強要しかねない記事タイトルだけでもう論外
そもそもコロナ前から普通にマスクしてたよね?やたら日本人日本人言うけどこの人は外国籍なのかな?
「マスクでウィルスが培養される」とか言う意見もあったが【生きた細胞なし】に【ウィルスが自己増殖できる】とかそれこそ新発見だよとしかwwww
病院の待合室とかはマスク付けるけど他はお願いされてない場所なら外すようになったわ。もっとこういうの流行っていいと思うけどトラブルの元と考えるとつけっぱなしが無難な人が多いのは最早国民性としか言いようがない。最近は暖かくなってきたけど冬場は眼鏡曇るし夏は暑苦しく熱中症の危険性もあるので好きなようにマスク外してどうぞ。
今年の花粉量は過去最大級、去年の約12倍だってさwww反マスクのアホどもザマああwww
化粧は手抜きできるし、商談・会議でも顔全体で表情作る必要がないし。ぶっちゃけ、人付き合いのある一般的な社会人としてはマスクしてた方が楽、まであるんだが。
おう、「任意」なんだよな?
飛行機で暴れて逮捕されたのがそんなに悔しかったのかwww
長々と書いているけど、大体どこの国にも当てはまる当たり前の事しか書いてないな




コメント
コメントする